Introduction
近年、『スマートシティ』という言葉を耳にする機会が増えました。これは、都市全体が高度なデジタル技術によって管理・運営されることで、都市機能を最適化した未来型のまちづくりのことです。
スマートシティ構想は、すでに各地域で具体的な取り組みがはじまっていて、実現段階へと移行しつつあります。
この記事では、スマートシティの概要と実現により得られるメリット、実現のために必要な技術や仕組み、課題などについて解説します。


目次
スマートシティとは?

まずは、スマートシティの概要と、よく似た用語との違いについてご説明します。
デジタル技術を活用して、よりよいサービスや生活の質を提供する都市・地域のこと
スマートシティとは、デジタル技術を活用し、そこで生活する人々によりよいサービスや生活の質を提供する、都市や地域のことです。
内閣府の『スマートシティとは』によると、以下のように定義されています。
スマートシティ
グローバルな諸課題や都市や地域の抱えるローカルな諸課題の解決、また新たな価値の創出を目指して、ICT 等の新技術や官民各種のデータを有効に活用した各種分野におけるマネジメント(計画、整備、管理・運営等)が行われ、社会、経済、環境の側面から、現在および将来にわたって、人々(住民、企業、訪問者)により良いサービスや生活の質を提供する都市または地域
都市開発にAI(人工知能)やICT(情報通信技術)などを活用することで、さまざまな課題の解決が期待されています。
たとえば、店舗の無人化や無人決済が普及することで人手不足の解消につながり、自動運転技術の普及により渋滞緩和効果を期待できます。また、河川の水位を自動監視するシステムを導入して災害対策を行う、過疎化が進む地方でセンサーカメラなどを活用して高齢者を見守るといった取り組みも実現可能です。さらに、マイナンバーカードの普及が広がることで行政手続きのオンライン化や行政運営の簡素化・効率化が進み、住民が行政サービスを利用しやすくなっています。
政府によるデジタル技術を活用した都市計画の具体的な取り組みとして、デジタル庁の「デジタル田園都市国家構想」があります。デジタル田園都市国家構想とは、「心ゆたかな暮らし」(Well-Being)と「持続可能な環境・社会・経済」(Sustainability)を実現していく構想で、大規模な地方創生策の一環として進められています。具体的には、全国のさまざまなエリアでデータを活用した街づくりを進めるために、防災や交通などのサービス間でデータ連携を行うための「データ連携基盤」の機能の提供を開始しています。
コンパクトシティとの違い
スマートシティとよく似た用語に「コンパクトシティ」があります。両者の違いについて解説します。
スマートシティとコンパクトシティは、どちらも持続可能な都市づくりを目指す概念ですが、以下のとおり定義、目的、アプローチの仕方に明確な違いがあります。
スマートシティはIoTやAI、ビッグデータなどの先進技術を活用して、都市のインフラやサービスを効率化、最適化する都市のことです。技術革新によって都市全体の運営を効率化して環境・経済・社会の課題を解決することを目的としています。アプローチの仕方としてはセンサー、クラウド、AIなどのデジタル技術や、ICT(情報通信技術)を活用した方法が中心です。
一方でコンパクトシティは、都市機能を都市の中心部や特定の拠点に集約して、土地を効率的に利用し、公共交通の利便性を追求した都市のことです。都市の無秩序な拡大を防いでインフラコストを抑えつつ、利便性と持続可能性を高めることを目的としています。アプローチの仕方としては、都市計画、ゾーニング(用途地域の指定)が中心で、物理的な配置や交通網の設計に重点を置いています。
このように、両者は目的や手段が異なることがわかります。
スーパーシティとの違い
スマートシティとよく似た用語に「スーパーシティ」という言葉がありますが、何が違うのでしょうか?
日本政府は、2020年にスーパーシティ法という法案を成立させ、スーパーシティ構想を打ち立てました。内閣府の『「スーパーシティ」構想について』によると、スーパーシティ構想は以下のように定義されています。
スーパーシティ構想
I.以下のような領域(少なくとも5領域以上など)を広くカバーし、生活全般にまたがる。
①移動、②物流、③支払い、④行政、⑤医療・介護、⑥教育、⑦エネルギー・水、⑧環境・ゴミ、⑨防犯、⑩防災・安全
II.2030年頃に実現される未来社会での生活を加速実現する
― 域内は自動走行のみ、現金取扱い・紙書類なしなど
III.住民が参画し、住民目線でより良い未来社会の実現がなされるよう、ネットワークを最大限に利用する。
スーパーシティ構想の目玉は医療や交通などの分野における規制緩和と、未来都市構想です。一方、スマートシティは現行法のなかで、効率化や持続可能性を高めることを目的としているという点が異なります。
▽▽ SHIFTの官公庁向けサービスサイト 「SHIFT 公共ポータル」 ▽▽
SHIFTの公共事例集はこちらからダウンロードいただけます。
>>公共事例集のダウンロードページへ
スマートシティの実現によるメリット
内閣府は、スマートシティの実現イメージを、以下のように掲げています。
①データ利活用の円滑化:データ連携の質・量が向上
②都市経営の深度化:技術の高度化、人材育成
③分野間連携サービスの拡大:データ連携で先端的なサービス提供が進む
④持続可能性の向上:ビジネスの自立化、地域での経済循環の確率・向上
⑤国内外への横展開:全国各地、海外への展開
ここでは、具体的にどのような社会が実現されるのかを解説します。
生活の質(QOL)が向上する
スマートシティの実現で、生活する人々の生活の質が向上することが期待されています。たとえば、店舗に行かなくてもオンラインで買い物をして、新鮮な食材や料理などが自宅に届く、病院に行かなくても自宅でリモート診療を受けられるなどです。
このように、自動運転技術やネットワーク通信などのデジタル技術を活用することで、より多くのことが実現できるようになります。移動できる範囲が広がる、そもそも移動する必要がなくなる、待ち時間が減るなどの変化により、生活の質を高めていけるでしょう。
行政サービスの質が向上し、市民の利便性が高まる
スマートシティ化によって行政サービスの質が向上し、市民の利便性が高まることが期待されています。
行政サービスの各種申請を紙媒体で行うのではなく、必要なデータを連携した電子申請が充実することで、住民は申請時に毎回個人情報を紙に記載する必要がなくなります。また、ビジネスでは自治体との連携が必要になることが多いため、スマートシティ化で官民の連携が進むことで、ビジネスがより円滑に進められるようになるでしょう。
持続可能な街づくりができる
スマートシティ化が進むことで、現在だけでなく、将来的にも暮らしやすい都市を持続的に実現することが可能です。ICTの活用により、交通渋滞・高齢者の増加・エネルギー不足などの社会的な課題を解決していくことで、将来的にも人々が暮らしやすい街をつくっていけるでしょう。
自然災害のリスクを軽減できる
スマートシティ化を進めることは、自然災害への対策にも役立ちます。
たとえば、河川の水位や土砂崩れの状況などをセンサーカメラで監視し、異変があれば迅速に住民に周知できるシステムがあれば、災害対策として有効です。また、災害発生時に避難所の情報や必要な物資の情報などを共有するときにも役立てられるでしょう。
新たなビジネスチャンスが生まれる
スマートシティが実現すれば、分野を超えたビッグデータを共有しやすくなります。これにより、異なる分野へ参入がしやすくなる、他分野との連携が可能になるなど、ビジネスにおいても大きなメリットを得られます。その結果、新たなビジネスチャンスの創出にもつながるでしょう。
スマートシティの実現に向けて必要となる技術・仕組み

スマートシティを実現するためには、具体的にどのような技術や仕組みが必要なのでしょうか?
ここでは、AIやIoT、データの活用など、スマートシティの実現に必要な技術や仕組みについて説明します。
AIやIoTなどの先端技術
AIやIoTの技術は、スマートシティの実現のために必要不可欠な技術です。
大量のデータを機械学習やディープラーニングでAIに学習させることにより、AIが人間のむずかしい判断や分析を行うことが可能です。たとえば、自動運転車が最適なルートを選定するときには、道路状況や渋滞状況などの多くのデータを分析する際に、AIが活躍します。
また、街に設置されたIoTセンサーを用いて、住民同士の情報共有に役立てている事例もあります。センサーで天候や気温などをモニタリングすることで、各地域の気象情報を共有することも可能です。
データの収集・活用
ビッグデータを収集・活用して、スマートシティの実現に役立てている事例もあります。
新型コロナウイルスの感染防止対策として、街を行きかう人たちのデータを収集して分析し、人の動きを可視化する実証実験が行われたことがありました。
街路灯に設置されたカメラによる映像をAIが映像解析し、人の移動する方向、性別や年代などの属性、人数などの情報をリアルタイムで収集します。その結果を新型コロナの感染状況、気象データなどと組みあわせて分析することで、人の動きの傾向をとらえ、三密回避のための仕組みの検討が行われました。
このような膨大なデータを収集して分析する仕組みは、スマートシティの実現のために役立ちます。
官民連携のプラットフォーム
地域住民の生活の質を向上させるための施策として、行政と民間企業が連携しやすいプラットフォームの活用があげられます。
各地域のすべての住民がもれなくサービスを受けるためには、行政が保有する住民データが必要不可欠です。たとえば、高齢者向けの支援サービスを周知するためには、行政がもっている高齢者の情報が必要になります。
民間企業と行政が適切に連携するためには、行政が保有するさまざまなデータを蓄積し、加工・分析できるプラットフォームの構築が求められるのです。
データ連携基盤の導入
データ連携基盤とは、異なるシステムやアプリケーション同士でデータを効率的に共有、活用するための基盤のことです。これにはデータの収集、保存、分析、共有などを行うための技術やプロトコルも含まれており、API、クラウドサービス、データベースなどを組み合わせることでデータ連携が可能になります。
データ連携基盤を適切に導入することで、自治体がもつ多様なデータをスムーズに活用できるようになります。異なる部署や機関が持つデータを統合・分析することで、人口減少、高齢化、災害対策などの課題を効果的に解決することが可能です。さらに、住民の健康管理や福祉サービスなどの充実に役立てることもできます。
スマートシティの実現に向けた課題
スマートシティを実現するためには、多くの課題を解決する必要があります。ここでは、スマートシティ実現に向けた課題について解説します。
コストの負担
スマートシティを実現するためには、AIやIoTなどの技術、ビッグデータを活かせる仕組み、官民連携のためのプラットフォームなどが必要です。しかし、これらの新しいデジタル技術を導入したシステムを構築し、維持・運用していくためには多大なコストを負担しなくてはいけません。
データやシステムの管理
スマートシティ実現のためのデータを収集し、システムを構築できたとしても、維持・運用をつづけていく必要があります。そのためには、データやシステムの維持管理費用だけでなく、運用を行う人材なども確保しなくてはいけません。
地域特性にあわせた柔軟な都市設計
スマートシティは、それぞれの地域の特性にあわせて、柔軟に設計していく必要があります。
高齢者が多い街、積雪が多い街など、地域の特性はそれぞれ大きく異なります。そのため、住民が求めるサービスは地域によって異なり、地域の特性にあったサービスを実現することが大切です。
地域住民の理解と参加促進
スマートシティを実現するためには、その地域の住民の理解と参加が必要です。
地域住民がいままで利用してきたサービスが変わる場合は、どのように変わり、どのようなメリットを得られるのか、デメリットはないのかなどを詳しく説明し、賛同を得る必要があります。地域住民の理解を得られなければ、参加者を増やしていくことはむずかしいでしょう。
国内外でのスマートシティの事例
国内外で、実際にスマートシティ化が進んでいる事例についてご紹介します。
北海道札幌市
北海道札幌市では、ICTを活用したスマートシティ化を進めています。
たとえば、健康ポイント事業を実施し、健康寿命を延ばすために、住民が街を歩くと健康ポイントがたまる専用アプリを開発しました。また、このアプリからデータを収集して、まちづくりに活かしています。
富山県富山市
富山県富山市では、2007年にコンパクトシティ戦略を打ち出し、さらに2018年には、IoTの仕組みを活用したスマートシティの実現に着手しています。
省電力のネットワークを地域に敷設し、個人情報以外の情報を取得して分析し、地域における新しい価値の創出に活かす試みを行っています。たとえば、子どもの通学路の安全を確保するための仕組みや、道路工事や除雪の状況をリアルタイムにできるシステムなどです。
シンガポール
シンガポールは、スマートシティ先進国です。
たとえば、コロナワクチンなどの予防接種の情報がSMSで届き、オンライン予約が可能で、環境省のアプリから気象情報のアラートが届きます。このような取り組みは、国家主導で行われています。
SHIFTの公共事例集
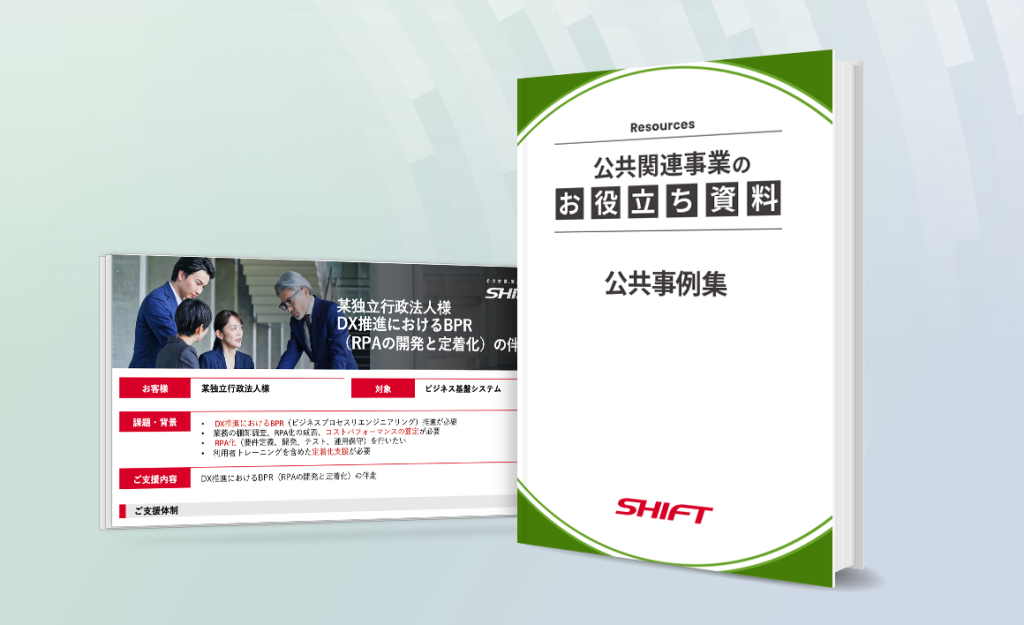
中央省庁様の感染対策システムのプロジェクト立ち上げ~品質改善支援。独立行政法人様のDX推進におけるRPAの開発と定着化など、各プロジェクトの課題や背景、ご支援体制、実現したことなど、事例の一部をまとめています。
官公庁でDXを進めるにあたっての豊富な経験から、多数のご支援を進めておりますので、お困りごとなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
中央省庁様の感染対策システムのプロジェクト立ち上げ~品質改善支援。独立行政法人様のDX推進におけるRPAの開発と定着化など、各プロジェクトの課題や背景、ご支援体制、実現したことなど、事例の一部をまとめています。
官公庁でDXを進めるにあたっての豊富な経験から、多数のご支援を進めておりますので、お困りごとなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
スマートシティとは、デジタル技術を活用して、そこで生活する人々によりよいサービスや生活の質を提供する、都市や地域のことです。
スマートシティ実現のためには、AIやIoT、ビッグデータの活用など、新しいデジタル技術の導入が必要不可欠です。今後、新たなデジタル技術や仕組みを活かして、各地域のスマートシティ化が進むことで、地域住民が生活しやすくなっていくでしょう。
スマートシティの仕組みを導入したい場合は、SHIFTの官公庁向けサービスをご活用ください。それぞれのニーズやシステム環境にあった対応を行い、お客様のDX推進を強力にサポートいたします。
SHIFT公共ポータルのページへ
行政システムのDX推進は、SHIFTにご相談を!
「IoTやAIの技術を活用して、スマートシティを実現したい」、「新しい技術のノウハウがなく、DXに対応できる人材がいない」などの悩みをもつケースも多いでしょう。
この記事でもご紹介したとおり、スマートシティの取り組みは全国各地で進んでいます。それぞれの地域に適したスマートシティが実現すれば、住民が暮らしやすい街になるでしょう。
しかし、AIやIoTなどの新しい技術を街づくりに活かすためには、専門的な知識や技術、ノウハウが必要です。IT人材が不足しており、AIの仕組みやビッグデータを活用できるシステムを導入するのがむずかしい、というケースも多いかもしれません。
SHIFTの官公庁向けサービスをご活用いただければ、行政のDX推進に関する課題を解決いたします。SHIFTがもつ行政システムの専門家や官公庁出身者の知見、課題解決に必要な技術を活かしてお客様の課題解決を支援いたします。
SHIFT公共ポータルのページへ


