Introduction
近年、生成AIの技術が進歩し、ChatGPTや画像生成ツール、自動音声によるニュースの読みあげなど、身近なところで見られるようになりました。しかし、便利な技術である一方、生成AIで生み出されたコンテンツの品質に問題があるケースや、著作権、倫理面での問題などについても考慮が必要です。
この記事では、生成AIの基本的な仕組みや実現できること、生成aiサービスの種類、ビジネスでの活用事例、そして利用する上でのメリット・デメリットまでを初心者にもわかりやすく解説します。この記事を読めば、生成AIの全体像を理解し、ビジネス活用の第一歩を踏み出すための知識が身につくでしょう。
※2025年11月の情報を基に作成しています。


目次
生成AIとは?
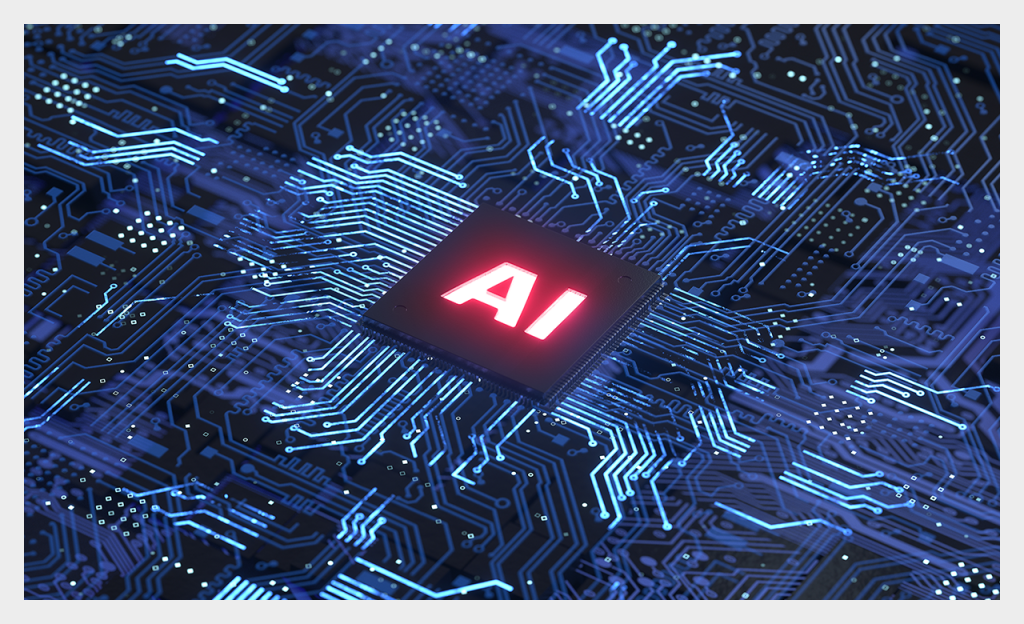
近年、生成AIの技術が著しく進化し、人々の生活に身近に感じるようになりました。しかし、生成AIとは具体的に何をできるものなのか、どのようなものがあるのか、実はよくわかっていないという人も多いでしょう。
ここでは、生成AIとは何か、その定義から解説していきます。
▽おすすめ資料▽
「わかったふりからの卒業「ヒンシツ大学 生成AI活用スキル習得講座」のご案内」
SHIFTが培ったナレッジを言語化・体系化した教育専門機関「ヒンシツ大学」の生成AI講座に関する資料です。生成AIの活用スキルを身につけ、業界のリーダーへと成長するための特別な講座をご紹介します。
>>「わかったふりからの卒業「ヒンシツ大学 生成AI活用スキル習得講座」のご案内」のダウンロードページへ
学習データからさまざまな新しいコンテンツを生成できるAIのこと
生成AIとは、機械学習や深層学習(ディープラーニング)の技術を用いて、インターネット上のテキストや画像、音楽などの膨大なデータを学習し、それらのデータに含まれるパターンや関連性を基に、全く新しいオリジナルのコンテンツを自動で生成する技術です。
生成AIが人間のように創造的なコンテンツを作れるのは、大量のデータを学習し、その知識を活用するからです。例えば、世界中の猫の画像を大量に学習させることで、そのデータから「猫らしさ」のパターンを抽出し、「宇宙服を着た猫」といった、これまで存在しなかった新しい画像を生成することが可能です。
生成AIの応用範囲は非常に広く、プログラムコードの生成、ニュース記事の作成、広告デザインの制作など、すでに私たちの身近な多くの場面で活用されています。今後も技術の進化に伴い、その活躍の場はさらに広がっていくことが予想されます。
機械学習についてはこちらもご覧ください。
>>機械学習とは?AIやディープラーニングとの違い、活用事例などを解説のページへ
深層学習(ディープラーニング)についてはこちらもご覧ください。
>>ディープラーニングとは?機械学習との違いやできること、活用事例を解説のページへ
従来のAI(識別系AI)との違い
生成AIと従来のAIは、実現できることやその仕組みがまったく異なります。ここでは、従来のAIを生成AIと区別するために、「識別系AI」と呼びます。両者はどちらも大量のデータを学習して何かをアウトプットするという点では共通していますが、その目的が大きく異なります。
識別系AIの主な役割は、与えられたデータが「何であるか」を識別・分類することです。例えば、画像データから「犬」か「猫」かを判別したり、音声データから特定の単語を認識したり、工場の製品画像から不良品を検出したりするのが識別系AIの得意分野です。これは、あらかじめ決められたルールや正解に基づいて、作業を自動化・効率化することに主眼が置かれています。
一方、生成AIの役割は、学習したデータから全く新しいものを「創造(Generate)」することです。大量のデータのパターンや関係性を学習し、それらを組み合わせて新たなテキスト、画像、アイデアなどをゼロから生み出します。
|
観点 |
識別系AI(従来のAI) |
生成AI |
|
主な役割 |
データが「何であるか」を識別・分類する |
学習したデータから新しいコンテンツを“創造”する |
|
動作イメージ |
正解(教師データ)に基づき、入力の分類・予測を行う |
パターンを踏まえて、新しい文章・画像・音声などを生成する |
|
具体例 |
・画像から犬/猫を判別・音声から単語を認識・製品画像から不良品を検出 |
・文章生成(ChatGPT)・画像生成(Midjourney)・アイデア生成・プログラムコード生成 |
|
目的 |
作業の自動化・効率化 |
クリエイティブ業務の補助・拡張 |
|
得意分野 |
分析・分類・予測 |
文章・画像・音声・動画などの生成 |
|
特徴 |
ルールや正解が明確なタスクに強い |
人間の創造性をサポートし、ゼロから新しいものを生み出す |
このように、識別系AIが「分析・分類・予測」による作業の自動化を得意とするのに対し、生成AIは「創造」によって人間のクリエイティブな活動を支援・拡張する点で、根本的に異なっています。
生成AIが注目されている理由
生成AIが注目されるのは、誰でも専門知識なしで使えるようになったこと、文章作成やデザインなどの創造的な作業を自動化できるようになったこと、そして新しいビジネスモデルを生み出す可能性をもっているためです。2022年に登場したChatGPTをはじめとする多くの生成AIサービスは、特別な専門知識や高価な機材がなくても、Webブラウザを通じて直感的に操作できます。これにより、技術者だけでなく、あらゆる職種の人々がAIの恩恵を受けられるようになりました。これらにより、業務効率化から新規事業創出まで幅広い分野で大きな影響を与える技術として期待されています。
生成AIの仕組みは?
生成AIが、まるで人間のように自然な文章や美しい画像を生成できるのはなぜでしょうか。その裏側には、高度な計算処理がありますが、基本的な仕組みは大きく2つのステップに分けることができます。ここでは、その仕組みを分かりやすく解説します。
大量のデータからパターンを学習する
生成AIの能力の源泉は、インターネット上の膨大なテキストや画像、コードなどのデータを学習することにあります。このプロセスは「ディープラーニング(深層学習)」と呼ばれる技術を用いて行われます。
AIは、人間の脳の神経回路を模した「ニューラルネットワーク」という仕組みを使い、与えられたデータのなかから単語と単語のつながりや、画像内の物体の特徴といった、無数のパターンや法則性を見つけ出します。例えば、文章を学習する場合、「『空』は『青い』」や「『リンゴ』は『赤い』」といった関係性を統計的に学びます。この学習量が膨大であるため、非常に複雑で多様な文脈や知識を吸収することができるのです。
入力された指示に沿ってアウトプットを生成する
学習が完了したAIは、ユーザーからの指示(プロンプト)を受け取ると、その内容に最も適したアウトプットを生成します。これは、学習した膨大なパターンのなかから、「次に来る確率が最も高い単語は何か」あるいは「このテキストに最も合致する画像の要素は何か」を連続的に予測していくことで行われます。
スマートフォンの予測変換機能をイメージすると分かりやすいかもしれません。「ありがとう」と入力すると「ございます」が候補に挙がるように、生成AIははるかに高度で複雑な文脈を理解し、単語やピクセルを一つひとつ丁寧につなぎ合わせることで、自然で創造的なコンテンツを生み出しているのです。
生成AIができること
生成AIが実現できることは多く、今後も活躍の場は広がっていくでしょう。ここでは、具体的にどのようなことができるのか、その簡単な仕組みや活用事例について解説します。
テキスト生成
テキスト生成とは、質問をテキストで入力すると、その答えが返ってくるものです。Web上の情報を学習し、質問に対して回答を生成して答える仕組みのものが多い傾向にあります。
近年、注目されているのが「ChatGPT」です。たとえば「○○という商品はどんなもの?」と質問をすると、製造年やメーカー、商品の内容などを答えてくれます。「○○ができるプログラムを○○言語で作成して」などのお願いをすると、動くプログラムを返してくれるなどの使い方もできます。このような機能を無料で使えるため、爆発的に広まりました。
ChatGPTについてはこちらもご覧ください。
>>ChatGPTとは?GPT-4oができること、メリット・注意点をわかりやすく解説のページへ
画像生成
画像を生成してくれる生成AIもあります。たとえば「エキゾチックな雰囲気の女性」と入力すると、異国風の衣装を身にまとった女性の画像が返ってくるなどです。
画像生成もテキスト生成と同様に、Web上の画像データなどを学習して、オリジナル画像を生成してくれます。ただし、インプット情報を誤認識したり、学習データが偏っていたりすると、見当違いの画像を返してくる点に注意が必要です。
代表的な画像生成サービスには「Midjourney」や「Stable Diffusion」があり、広告のクリエイティブ制作やデザインのアイデア出しなどに活用されています。
画像生成AIについてはこちらもご覧ください。
>>画像生成AIとは?ビジネスでの活用事例や注意点、代表的なモデルを解説のページへ
動画生成
画像生成の進化版として、動画生成AIも存在します。画像生成と同様に、イメージをテキストで入力すると動画を返してくれたり、入力した動画を新しくつくり変えてくれたりするものです。例えば、「ドローンで撮影したような、桜並木を駆け抜ける映像」といった指示で、数秒から1分程度の短い動画クリップを作成できます。まだ発展途上の技術ですが、SNS用のショート動画制作や広告映像のプロトタイプ作成などでの活用が期待されています。代表的なサービスとして、OpenAI社の「Sora」やRunway社の「Gen-2」などがあります。
音声生成
音声データを入力すると、その音声を使った新しい音声データを生成してくれる音声生成AIもあります。Microsoft社の「VALL-E」は、たった3秒間の音声サンプルがあれば、その音声による声を忠実に再現してくれます。具体的な活用例としては、ニュース記事の自動読み上げ、オーディオブックの制作、動画のナレーション作成などが挙げられます。また、亡くなった俳優や声優による音声の再現などが可能です。
プログラムコード生成
生成AIは、プログラミングのコードを自動で生成することも得意としています。例えば、「顧客リストを名前順で並び替えるPythonのコードを書いて」のように、自然な言葉で指示するだけで、そのまま実行可能なコードを生成してくれます。
これにより、専門的なプログラマーでなくても簡単なツールを作成したり、既存のコードの間違いを発見・修正したりすることが容易になります。開発業務の大幅な効率化に繋がり「GitHub Copilot」などのサービスが多くのエンジニアに利用されています。
各生成AIに搭載されている裏側のAIモデルについては下記記事をご確認ください。

【分野別】代表的な生成AIサービス
生成AIの技術は、世界中の企業が開発したさまざまなサービスを通じて利用することができます。ここでは、分野別に代表的な生成AIサービスを紹介します。多くは無料または試用期間付きで利用できるため、気軽に試してみてはいかがでしょうか。
テキスト生成(ChatGPT、Geminiなど)
対話形式で文章を生成するAIは、現在最も普及しているタイプです。
・ChatGPT (OpenAI社): 生成AIブームの火付け役となった、最も有名な対話型AI。質問応答、文章作成、翻訳、要約、アイデア出しなど、幅広いタスクに対応できます。
・Gemini (Google社): Googleが開発した対話型AI。Google検索と連携し、最新の情報に基づいた回答を生成できるのが強みです。
・Claude (Anthropic社): より自然で倫理的な対話を重視して開発されたAI。特に長い文章の読解や生成が得意とされています。
画像生成(Midjourney、Stable Diffusionなど)
テキストから画像を生成するサービスは、クリエイティブな分野で広く活用されています。
・Midjourney: アーティスティックで高品質な画像の生成に定評があるサービス。Discordというチャットアプリを通じて利用します。
・Stable Diffusion (Stability AI社): オープンソースで公開されており、無料で利用できる環境も多いのが特徴。カスタマイズ性が高く、多くの関連ツールが開発されています。
・DALL-E 3 (OpenAI社): ChatGPTに統合されており、対話の流れで画像を生成できるのが特徴。指示の理解度が高いと評価されています。
動画生成(Sora、Pikaなど)
動画生成は急速に技術が進化している分野で、今後の活用が期待されています。
・Sora (OpenAI社): ChatGPT PlusまたはProユーザーが利用でき、テキストによる指示から高品質な動画を生成するAIのことです。2025年11月時点では限定公開となっております。
・Pika (Pika Labs社): テキストや画像から短い動画を生成するサービス。Webブラウザから手軽に利用できます。
・Runway Gen-2 (Runway社): 動画生成AIの先駆けの一つ。テキストからの生成に加え、既存の動画のスタイルを変換するなど多機能です。
音声生成(ElevenLabs、CoeFontなど)
テキスト読み上げや音声合成の分野でも、高品質なサービスが登場しています。
・ElevenLabs: 非常に人間らしく自然な音声合成が可能で、多言語に対応しています。自分の声を複製する機能もあります。
・CoeFont: 日本語に特化した音声合成プラットフォーム。5,000種類以上のアニメ声や有名人の声を利用できるのが特徴です。
生成AIのビジネス活用事例
生成AIは、すでに多くの業界で業務効率化や新しい価値の創出に貢献しています。ここでは、具体的なビジネスシーンでの活用事例を3つの分野に分けて紹介します。
マーケティング・広告
マーケティング分野では、コンテンツ制作の効率化とパーソナライズに生成AIが大きく貢献しています。
・広告コピー・画像制作: ターゲット層や商品の特徴を指示するだけで、キャッチコピーや広告バナーの画像を複数パターン自動生成できます。これにより、A/Bテストを効率的に行い、広告効果を最大化することが可能です。
・SNS投稿の自動生成: キャンペーン内容やイベント情報を入力し、定期的なSNS投稿の文面やハッシュタグを自動で作成。運用担当者の負担を大幅に軽減します。
・ブログ記事・メルマガ作成: SEOキーワードやテーマを指示し、記事やメルマガの草案を生成。一から文章を考える時間を短縮し、コンテンツの量産を支援します。
開発・エンジニアリング
ソフトウェア開発の現場では、生成AIがコーディング作業を強力にサポートします。
・コード生成と補完:「こういう機能が欲しい」と自然言語で指示するだけで、適切なプログラムコードを生成します。開発効率が飛躍的に向上し、開発期間の短縮につながります。
・デバッグ(バグ修正): エラーが発生したコードを提示し、「どこが間違っているか」を質問すると、問題箇所を特定し、修正案を提示してくれます。
・技術仕様書の作成:コードの内容を読み込ませ、その機能や使い方をまとめたドキュメントを自動で生成。開発者が文書作成に費やす時間を削減します。
カスタマーサポート
カスタマーサポートの領域では、24時間365日対応可能なAIチャットボットが活躍しています。
- 問い合わせ自動応答: よくある質問(FAQ)の内容を学習させたAIが、顧客からの問い合わせに24時間リアルタイムで自動回答します。これにより、オペレーターはより複雑で専門的な問い合わせに集中できます。
- 応対内容の要約: 顧客との通話やチャットの履歴をAIが自動で要約し、データベースに記録。応対品質の分析や情報共有を効率化します。
- オペレーター
カスタマーサポートの領域では、24時間365日対応可能なAIチャットボットが活躍しています。
・問い合わせ自動応答: よくある質問(FAQ)の内容を学習させたAIが、顧客からの問い合わせに24時間リアルタイムで自動回答します。これにより、オペレーターはより複雑で専門的な問い合わせに集中できます。
・応対内容の要約: 顧客との通話やチャットの履歴をAIが自動で要約し、データベースに記録。応対品質の分析や情報共有を効率化します。
・オペレーター支援: 顧客からの質問内容に応じて、最適な回答文の候補をオペレーターの画面に表示。応対品質の均一化と新人教育の効率化に貢献します。
支援: 顧客からの質問内容に応じて、最適な回答文の候補をオペレーターの画面に表示。応対品質の均一化と新人教育の効率化に貢献します。
生成AIを利用するメリット
生成AIを利用することで、得られるメリットについてご説明します。
業務効率化ができる
もっとも大きなメリットとして、業務の効率化があります。生成AIを活用すれば、これまで人間が時間をかけて行っていた資料作成、データ集計、議事録作成といったさまざまな作業を自動化、または大幅に時間短縮することが可能です。
たとえば、コールセンター業務の負荷を削減するために、生成AIによるチャットツールを活用することがあります。単なる質問なら、チャットツールに質問することで解決することも多く、コールセンターの対応を減らすことが可能です。
コンテンツ制作にかかるコストを削減できる
画像や映像、テキスト情報などのコンテンツ制作のコスト削減も可能です。人間が一からコンテンツを制作するのではなく、生成AIを活用して自動生成し、それに手を加えることでコストを削減できるでしょう。
アイデアの創出と選択につながる
画像や映像、テキスト情報の構想を一から生み出すのはむずかしく、時間がかかることですが、生成AIを活用すればすぐにアウトプットしてくれます。人間だけでは思いつかなかったような斬新な視点や表現を得ることができ、企画会議やブレインストーミングの活性化につながります。またいくつかの選択肢に迷った場合AIにより最適解を導くサポートもしてもらえます。
プロトタイプを迅速に作成できる
プロトタイプ(試作品)をつくることで、はやめに問題を洗い出せる、構造や仕様を検討できるなどのメリットがあります。しかし、プロトタイプを作成するのも手間がかかります。そこで、生成AIを活用してプロトタイプを作成すれば、作成の手間を省くことが可能です。
たとえば、生成AIでプログラムのプロトタイプを作成し、それをたたき台にして問題を洗い出すなどの活用の仕方があります
顧客対応力を強化できる
問い合わせ対応時に、生成AIによるチャット対応を行うことで、簡単な質問や問い合わせに24時間365日対応することが可能です。これにより、顧客の待ち時間が短縮され満足度が向上します。結果として、人間の担当者はより複雑な対応に集中でき、顧客対応全体の質の強化につながるでしょう。
生成AIを利用するデメリット
生成AIにはメリットが多い一方で、デメリットがあることも忘れてはいけません。ここでは、生成AIを利用するデメリットについて解説します。
誤ったコンテンツが作成される可能性がある
生成AIで生み出されたコンテンツは、人が目を通しておらず、誤ったコンテンツが作成される可能性も十分にあります。生成AIが情報を誤って認識している、学習用データがそもそも間違っているなどの可能性もあるためです。
その妥当性の検証が困難な場合も多く、使用時には注意が必要です。
著作権や倫理面の問題に発展する可能性がある
生成AIが学習するデータには、著作権で保護されたコンテンツが含まれている場合があります。そのため、生成されたアウトプットが意図せず既存の著作物と酷似してしまい、著作権侵害にあたるリスクがあります。また、実在の人物の画像や音声を不正に利用して、偽情報(ディープフェイク)を作成するなど、倫理的な問題に発展するケースも懸念されます。
セキュリティ上のリスクが存在する
企業の機密情報や顧客の個人情報をプロンプトとして入力してしまうと、その情報がAIの学習データとして外部のサーバーに送信・保存され、情報漏洩につながるリスクがあります。多くの生成AIサービスでは入力されたデータを学習に利用しない設定も可能ですが、利用する際は企業のセキュリティポリシーを遵守することが不可欠です。
運用開始後に性能が劣化する場合がある
運用を開始した後に、新たな技術が別に登場することで、その技術と比べると性能が劣る場合もあります。生成AIは新しい技術であり、次から次へと優れた技術が登場します。そのため、つねに新しい情報にアンテナを張っておく必要があるでしょう。
人間の仕事を奪ってしまう場合がある
生成AIは、人間と同等、またはそれ以上の精度のコンテンツを生み出せる技術です。そのため、これまで人間が担ってきた定型的な業務や一部のクリエイティブな仕事がAIに代替され、人間の仕事が奪われてしまう可能性も指摘されています。
生成AIを安全に活用するためのポイント
生成AIを安全に活用するために、押さえておきたいポイントについてご説明します。
指示内容を変えながら、回答の精度を高める
生成AIは、与えるインプットが非常に重要です。質問内容が悪いと、それなりの回答しか返ってきません。期待通りの回答が得られない場合は、一度で諦めずに、より具体的で明確な指示を出したり、役割を与えたり、前提条件を変えたりするなど、さまざまな角度から指示内容を工夫し、対話を繰り返すことで回答の精度を高めていくことが重要です。
人力での検証・編集作業をはさむ
すべてを生成AIに任せるのではなく、アウトプットを人の目で検証し、編集することで精度を高めることも重要です。 AIが生成したアウトプットはあくまで「下書き」や「たたき台」として捉えることが重要です。誤った情報が含まれていないか、著作権を侵害していないか、表現は適切かなど、最終的には必ず人間の目で検証し、編集・修正を加えるプロセスを挟むことで、品質と安全性を担保することができます。
生成AIを使ったシステム開発では品質保証を行う
生成AIを使ってシステム開発を行う場合は、品質保証作業が欠かせません。従来のシステムテストに加え、AIが予期せぬ不適切な出力をしないか、特定のバイアスをもっていないかなど、AI特有のリスクを想定した多角的な検証が求められます。信頼性と安全性の高いシステムを構築するためには、専門家による質の高い品質保証を行うことが重要です。
SHIFTのAI品質保証サービスについて
SHIFTの「AI特化型品質保証サービス」は、生成AIや機械学習を活用するプロジェクトに対して、出力の妥当性・モデルの振る舞い・システム全体の品質保証までを一貫して支援します。独自のAI品質保証フレームワークとテスト手法を用い、予期しない誤出力や劣化リスクを含むAI特有の課題にも対応します。
AIシステムの品質保証
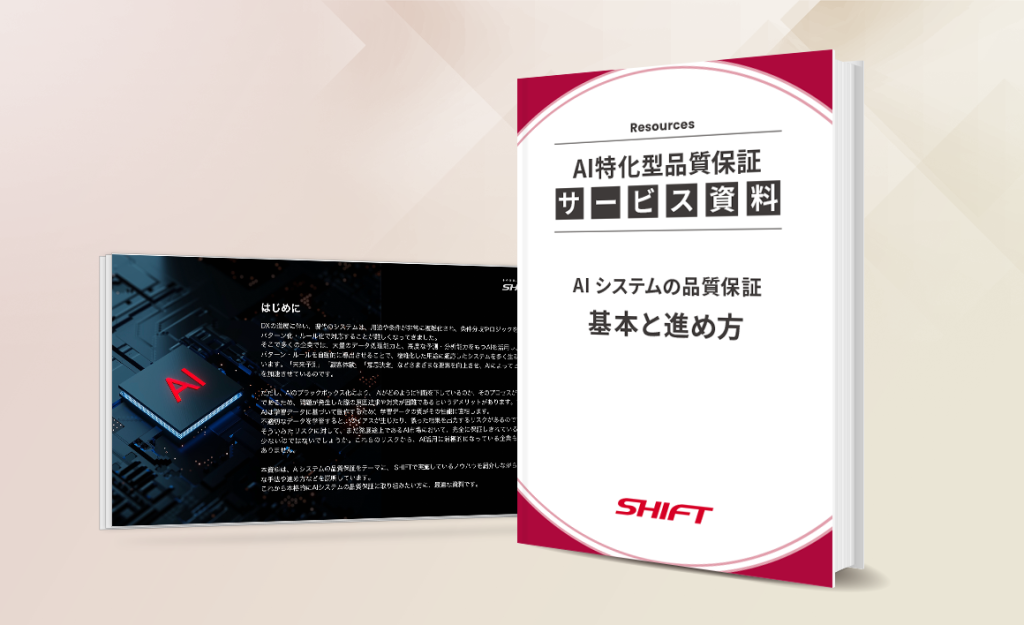
本資料は、AIシステムの品質保証をテーマに、 SHIFTで実施しているノウハウを紹介しながら具体的な手法や進め方などを説明しています。
AIシステムの安全性と信頼性を確保することで、ユーザーに安心感を提供し、その結果、より広範囲での利用を促進いただけます。品質が確保されたAIシステムは、予測精度が高まり、ビジネスの意思決定や社会問題の解決に大きく貢献します。ぜひご覧ください。
本資料は、AIシステムの品質保証をテーマに、 SHIFTで実施しているノウハウを紹介しながら具体的な手法や進め方などを説明しています。
AIシステムの安全性と信頼性を確保することで、ユーザーに安心感を提供し、その結果、より広範囲での利用を促進いただけます。品質が確保されたAIシステムは、予測精度が高まり、ビジネスの意思決定や社会問題の解決に大きく貢献します。ぜひご覧ください。
まとめ
この記事では、生成AIで実現できること、その仕組みや代表的なサービス、生成AIを利用するメリット・デメリットなどについて解説しました。
生成AIは、業務効率化や新たな価値創造の可能性を秘めた非常に便利な技術です。一方で、情報の正確性や著作権、セキュリティといったリスクも存在するため、その特性を正しく理解し、注意深く活用する必要があります。
SHIFTでは、AIシステムに特化した品質保証フレームワークの導入を行い、安全性の高いシステム開発を一気通貫で支援しています。AIシステムの品質担保が課題、AIを安全に活用したいという場合は、SHIFTにお気軽にご相談ください。
>>AI特化型品質保証サービスのページへ
>>お問い合わせページへ
>>料金についてページへ

