Introduction
近年、ビジネスや政治などの分野でDXが推進されていて、防災の分野でもデジタル技術の活用の取り組みが進められてきました。デジタル技術を活用して災害対応の効率化と高度化をはかるこのような取り組みは、防災DXと呼ばれます。
この記事では、防災DXとは何か、導入するメリットや課題、国や自治体の具体的な取り組み事例などについて解説します。


目次
防災DXとは

防災DXとはどのようなものなのか、いまなぜ注目されているのかについて解説します。
デジタル技術を活用して防災業務をよりよいものへ変革すること
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して業務の効率化や生産性の向上をはかり、企業や組織を変革して競争力を高めることを指します。
防災DXとは、防災対策にデジタル技術を取り入れることで、災害対応の効率化を目指す取り組みです。予測しにくい災害にデジタル技術を活用することで、防災対策を強化します。
具体的には、災害発生時にリアルタイムの情報を共有できる防災アプリの開発、ドローンとAIによる災害現場の調査・分析などの取り組みが行われています。
DXについてはこちらもご覧ください。
>>DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?なぜ必要なのか、進め方もあわせて解説のページへ
防災DXがなぜ注目されているのか
災害大国といわれる日本では、地震・津波・洪水などのさまざまな災害発生要因が存在しています。しかし、その一方で少子高齢化や施設の老朽化、生活スタイルの多様化などが進み、災害に対する脆弱性が増大していることも事実です。
このような状況を打破するためには、デジタル技術を活用し、効果的な新しい方法で災害に強い社会を実現する、防災DXの取り組みが必要といえるでしょう。
▽▽ SHIFTの官公庁向けサービスサイト 「SHIFT 公共ポータル」 ▽▽
SHIFTの公共事例集はこちらからダウンロードいただけます。
>>公共事例集のダウンロードページへ
防災DXに取り組むメリット
防災DXに取り組むことで得られるメリットについてご説明します。
情報を迅速に伝達できる
災害現場では、刻々と変わっていく現場の状況を正確に把握することが非常に重要です。どこに何人被災者がいるのか、けが人や病人はいるのか、何が足らないのかなどの情報を迅速に伝えなければなりません。
デジタル技術を活用して情報共有を行うアプリなどを開発・運用することで、情報を迅速に伝達できるようになります。
被害状況を迅速かつ正確に把握できる
ドローンなどで収集した被災地の情報を分析することで、リアルタイムの情報を収集できます。その情報をもとに災害対策本部から迅速に指令を出すことで、初動対応がより適切なものとなるでしょう。
避難所の管理を効率化できる
災害発生時には、避難所で多くの人たちが過ごすことになります。その際に、避難所にいる人の人数や、高齢者・こども・けが人や病人の状況などを把握しないと、必要な食料・薬・衣服などを適切に提供できません。
このようなときに、情報を収集して共有するシステムを活用することで、避難所のリアルタイムな情報を自治体や災害対策本部と共有できれば、避難所の管理の効率化を進められるでしょう。
行政サービスを効率化できる
災害発生時にはその地域の自治体職員も被災するため、自治体の窓口業務が滞り、罹災証明書の発行などの手続きに影響がでます。
罹災証明書発行手続きや問い合わせ対応などをデジタル化すれば、被災時にも行政サービスを効率的に提供することが可能です。また、被災した自治体職員や被災者の負担軽減にもつながります。
防災DXを実現するための具体的な技術・ツール
防災DXを実現するために用いられる、具体的な技術やツールについてご紹介します。
防災アプリ
地域住民向けの防災アプリがあれば、河川の氾濫情報や避難所の開設情報などの防災関連情報を、住民が手軽に入手できます。防災アプリは高齢者やこどもなども利用しやすいように、視覚的にわかりやすく、誰でも必要な情報を収集できるようになっています。
SNS
災害発生時にはSNS上で、「ライオンが動物園から逃げ出した」「〇〇町〇-〇の建物が倒壊してなかに人がとり残されています」など、虚偽情報や悪質なデマが拡散されることも少なくありません。そこで、AIがSNSの情報を解析して信ぴょう性を確認しながら情報を収集できるサービスの開発が進んでいます。
たとえば、「FASTALERT(ファストアラート)」というAI情報収集ツールを活用すれば、必要なリアルタイムの情報を把握できます。
AIチャットボット
災害が起こると罹災証明書の発行や支援の申請など、自治体へ問い合わせや申請を行う機会が増えます。自治体の公式サイトなどにAIチャットボットを設置すれば、住民が必要な情報を手軽に得ることが可能です。
また、自治体職員が住民からの問い合わせに対応する負担を軽減できるところもメリットです。
クラウドシステム
自治体が保有する情報やシステムをクラウド化しておけば、災害時に自治体の建物が被災しても、重要なデータやシステムは失われません。災害後も自治体の機能が停止することなく、継続的にサービスを提供できるでしょう。
地理情報システム(GIS)
GISとは「Geographic Information System」の略で、地図に情報を重ねて地図情報の編集や検索、分析などを行うシステムです。とくに水害の対策に役立つシステムで、もともと予測されていた浸水地域と、実際に浸水が起きた地域を重ねることで、より精度の高い水害対策が実現できるでしょう。
ドローン
被災地の状況確認を行うためには、ドローン役立ちます。地上からは確認しにくい崖崩れや海岸線、山間などの状況も、ドローンを活用すれば詳細に確認できます。
防災DXに取り組むうえでの課題

防災DXに取り組む際に検討しておくべき課題について解説します。
自治体間での防災システムの標準化
それぞれの自治体で防災システムの導入が進んでいますが、システムの標準化がいまだに進んでいないという状況があります。そのため、国と自治体や自治体間の連携がとりにくく、災害発生時に被害状況や対応状況を一元的に管理することがむずかしいのが現状です。
国や自治体同士の連携を強めるためには、防災システムの標準化を進めていかなければなりません。
DX人材・ノウハウの不足
人手不足が慢性化しているため、防災DXを推進できるDX人材を確保するのがむずかしいという問題もあります。そのため、日ごろから専門的な知識やスキルを備えたDX人材の確保や人材教育を進めていく必要があるでしょう。
システムの導入・維持のコスト
防災DXを進めるためにはシステムやツール類の導入が必要不可欠であり、導入した後もメンテナンスや運用を行うためのコストがかかります。そのため、導入コストや運用コストについて、適切に見積もっておくことが重要です。
住民のデジタルリテラシー向上の必要性
防災関連のデジタルツールを自治体が導入しても、住民が使いこなせないと役に立ちません。そのため、誰でも使いやすいデジタルツールを開発し、住民のデジタルリテラシー向上のための取り組みを行うことも求められています。
普段から防災アプリやツールについて住民に周知する、使ってもらうための機会をもうける、などの対策を進めておく必要があるでしょう。
国や自治体が実施している防災DXの取り組み
国や自治体が実際に実施している防災DXの取り組みを紹介します。
「防災DX官民共創協議会(BDX)」の発足
防災対策に関して国だけでなく地方公共団体や民間企業の参画も促すために、2022年12月に「防災DX官民共創協議会」が発足し、防災DXの取り組みを進めています。
2024年1月1日に石川県能登地方を中心に最大震度7の地震が発生したため、防災DX官民共創協議会はデータ連携のために必要な支援活動を行いました。この地震で広いエリアの通信が途絶しましたが、衛星インターネット通信サービスのスターリンクを提供したため、自治体・消防・医療機関・ボランティア団体などの活動拠点で、通信の支援を実施できました。
また、車載360度カメラで撮影した映像を、災害情報を一元的に閲覧できる「防災クロスビュー」に提供することで、支援活動計画の立案に役立っています。
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の閣議決定
2023年6月にデジタル庁による「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が閣議決定されました。
防災の分野は、医療・教育・こどもなどがもうけられ、「準公共分野」に位置づけられました。平時・切迫時・応急時・復旧復興時という災害フェーズを通じて連携し、災害時に住民が適切な支援を受けられるようにデータ連携基盤を構築することが明記されています。
「防災DXサービスマップ」「防災DXサービスカタログ 」の公開
デジタル庁は、防災分野における民間サービスやアプリなどの情報をすばやく検索するために、「防災DXサービスマップ」や「防災DXサービスカタログ」を公開しています。災害の局面に応じてサービスを分類してつなげることで、緊急時に必要な情報を迅速に検索することが可能です。
【東京都】防災チャットボット「SOCDA」
防災チャットボット「SOCDA(ソクダ)」は、災害時に情報提供・共有をサポートするツールです。登録したユーザーの情報をもとにAIが最適な避難経路や避難場所を示してくれる避難支援機能、写真やテキストで被害状況を投稿できる情報投稿機能などが搭載されています。
また、災害対策本部がこれらの情報を集約して、適切な意思決定につなげることが可能です。
【愛知県豊橋市】AIリアルタイム防災 ・危機管理サービス「Spectee Pro」
「Spectee Pro」とは、SNS・気象情報・自動車のプローブデータ・道路や河川カメラなどの情報を解析し、災害情報を迅速に収集して可視化と予測ができる、AIリアルタイム防災・危機管理サービスです。必要な情報についてリアルタイムに通知を受け、正確で整理された情報を入手できます。
SHIFTの公共事例集
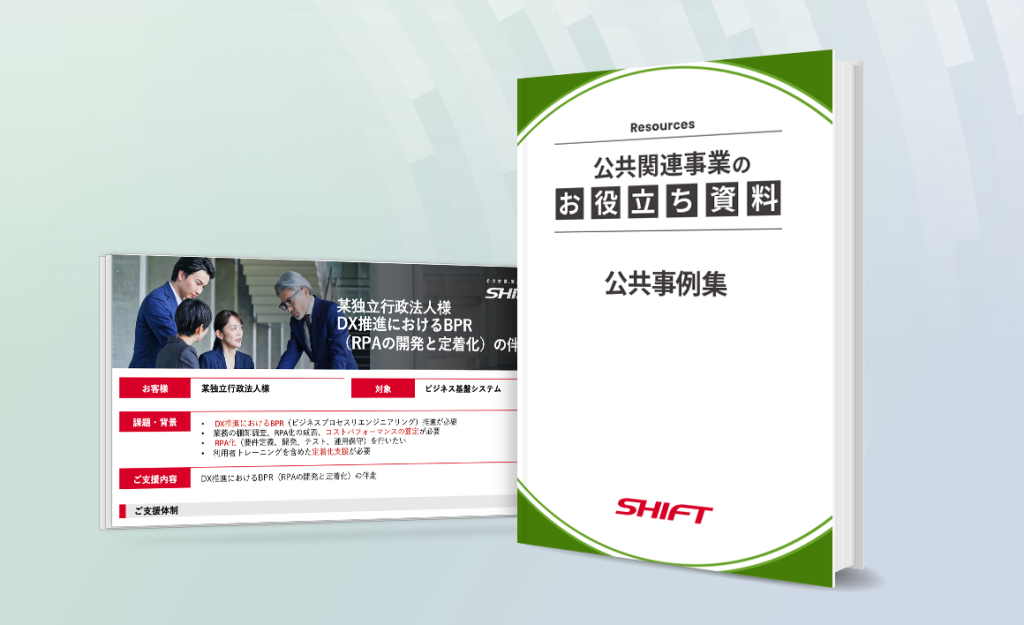
中央省庁様の感染対策システムのプロジェクト立ち上げ~品質改善支援。独立行政法人様のDX推進におけるRPAの開発と定着化など、各プロジェクトの課題や背景、ご支援体制、実現したことなど、事例の一部をまとめています。
官公庁でDXを進めるにあたっての豊富な経験から、多数のご支援を進めておりますので、お困りごとなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
中央省庁様の感染対策システムのプロジェクト立ち上げ~品質改善支援。独立行政法人様のDX推進におけるRPAの開発と定着化など、各プロジェクトの課題や背景、ご支援体制、実現したことなど、事例の一部をまとめています。
官公庁でDXを進めるにあたっての豊富な経験から、多数のご支援を進めておりますので、お困りごとなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
防災DXとは、防災対策にデジタル技術を取り入れることで、災害対応の効率化を目指す取り組みです。予測しにくい災害に対し、デジタル技術を活用して防災対策を強化します。
災害大国といわれる日本において、防災DXの推進は重要な施策といえるでしょう。
各自治体で防災DXを推進したい場合には、SHIFTの官公庁向けサービスをご活用ください。それぞれのニーズやシステム環境にあった対応を行い、行政のDX推進をサポートいたします。
SHIFT公共ポータルのページへ
行政システムのDX推進は、SHIFTにご相談を!
「防災DXを推進して、災害発生時に備えたい」「AIやビッグデータ活用のノウハウがなく、DXに対応できる人材がいない」などの悩みを抱える自治体も多いかもしれません。
この記事でご説明したとおり、災害に備えて行政主導の防災DXの取り組みが進められています。防災DXを推進するためにはデータの保持やシステムの冗長化など、災害に強いシステムへの刷新が必要ですが、そのためにDXの知識をもつ人材やノウハウが必要です。しかし、多くの自治体で職員不足が深刻化しており、IT人材を育成したり新たに技術者を採用したりするのがむずかしいケースも多いでしょう。
SHIFTの官公庁向けサービスをご活用いただければ、行政のDX推進に関する課題を解決いたします。SHIFTがもつ行政システムの専門家や官公庁出身者の知見、課題解決に必要な技術を活かして、お客様の課題解決を支援いたします。
SHIFT公共ポータルのページへ


