Introduction
API連携という言葉を耳にすることはあっても、具体的にそれがどういうことなのか、何を実現できるのかわからない方も多いのではないでしょうか。
API連携とは、アプリケーションの機能を別のアプリケーションから呼び出す際に役立つ仕組みです。API連携の仕組みを活用すれば、新たにアプリケーションやソフトウェアを開発しなくても、すでにあるものを利用することが可能です。API連携をすることで、開発コストの削減と業務の効率化を実現できます。
ここでは、API連携の仕組みやAPI連携を活用するメリットとデメリット、実際の活用事例などについて解説します。


目次
API連携とは?

API連携とは何か、そもそも、APIとは何かを説明します。
APIによって異なるシステム間でデータや機能を連携し、機能を拡張すること
APIとは、「Application Programming Interface」の略で、アプリケーションやプログラム同士をつなぐ機能のことです。
総務省公式サイトの『第1部 特集 進化するデジタル経済とその先にあるSociety 5.0』では、次のように説明されています。
API
APIとは、あるアプリケーションの機能やデータ等を他のアプリケーションからでも利用できるようにするための仕組みをいう。
Interface(インターフェース)は「境界線」や「接点」と訳され、APIはアプリケーション同士のインターフェースという意味になります。異なるアプリケーションやソフトウェア、プログラム同士をつなぐ役割を果たす部分です。
そして、API連携とは、APIを活用して異なるアプリケーションやソフトウェア、プログラム同士を連携させることを指します。
WebサイトにFacebookやX、LINEなどのSNSのボタンが設置されているのを見かけることがあります。このボタンをクリックすると、いま見ていたWebサイトの記事を、SNSの自分のアカウントで投稿できます。これは、Webサイト側がAPI連携機能を使いSNSの機能を呼び出して利用しているものです。
この連携ボタンを使えば、ユーザーは「WebサイトのURLをコピーしてSNSを起動し、URLを投稿画面に貼りつける」という手間をかけなくても、ワンクリックで投稿することが可能です。
このように、API連携機能を使えば、さまざまなアプリケーションやソフトウェア、プログラム同士を連携させられます。
API連携が求められる理由
さまざまな分野で多くのアプリケーションやシステムが開発され、ツール化が進んでいますが、それぞれのアプリケーションを個別に使うだけでは、ユーザーが便利に利用できません。そのため、API連携を活用してアプリケーション同士を連携させることが求められています。
たとえば、ECサイトで買い物をする際に、ECサイトのアプリケーションとは別に、QRコード決済アプリにログインして決済を行うのは非常に不便です。しかし実際はそのような手間をかけることなく、ECサイトで決済方法を選ぶとPayPayなどの決済アプリと連動し、スムーズに支払いが行えます。
また、ビジネスシーンにおいても、API連携は必要不可欠な仕組みです。たとえば、発注手続きを行う際に発注管理システムと決済システムを連携させることで、発注から決済までの手続きをワンストップで済ませることが可能です。
このように、多くのアプリケーションやソフトウェアが利用されるようになったことで、API連携の重要性が高まっています。
関連サービスについて
API連携のメリット
API連携を活用することで得られるメリットについて説明します。
業務効率化につながる
業務に利用しているアプリケーション同士や外部のシステムなどと連携させることで、業務の効率化につながります。たとえば、アプリケーションごとにデータを別々に用意する必要がなくデータを共有できる、それぞれのツールを別々に操作する必要がなくなり操作性が向上するなどのメリットを得られます。
データ活用が促進される
API連携を活用することで、それぞれのアプリケーションやシステムのなかに蓄積されているデータの連携が容易になります。その結果、データの加工や活用、共有などがしやすくなり、多くのメリットを得られるでしょう。
たとえば、複数のツールを連携させると、売上データの集計結果を迅速に報告できる、即座に分析を行い販売戦略に活かせるなどが可能です。
このように異なるアプリケーションやシステム間でデータを連携すると、ビジネスを進めやすくなるというメリットを得られます。
セキュリティが強化される
セキュリティレベルの高い既存の決済システムなどをAPI連携で活用することで、セキュリティを強化できます。
たとえば、ECサイトなどで決済処理のみ他システムを利用することで、自社システム内にクレジットカード情報などの重要な情報を保持する必要がなくなります。その結果、自社システムのセキュリティの強化につながります。
API連携のデメリット
API連携によって実現できることが増えると、多くのメリットを得られますが、注意すべきこともあります。ここでは、API連携のデメリットについて解説します。
APIの提供終了・仕様変更のリスクがある
API連携機能は、開発したアプリケーションやシステムを幅広く活用してもらうために、開発側が用意する機能です。
たとえば、XのAPI連携機能は、Xの開発側が用意しています。しかし、開発会社の方針が変わると、連携部分の仕様の変更やAPI連携の終了、場合によってはサービス自体が終了してしまうこともあります。
API連携を利用する場合には、API連携の仕様変更や提供終了のリスクを検討しておかなくてはいけません。
連携するアプリケーション側でトラブルが発生する場合もある
連携するアプリケーションで何らかのトラブルが発生すると、連携機能を利用する側には問題がなくても、連携がうまくいかなくなる場合があります。
とくに、ログイン認証機能や決済機能を外部ツールと連携して利用している場合、ログインや決済などの重要な機能を利用できなくなるため、大きな影響を受けるでしょう。
リクエスト回数に制限がかけられている場合がある
無償、または定額利用が可能なAPI連携機能では、リクエスト回数が制限されている場合があります。そのため、API連携を行う前に仕様や料金などについて詳しく調べ、問題なく利用できることを確認しておく必要があります。
かえってコストが膨れ上がる可能性もある
従量課金制のAPI連携機能の場合、使えば使うほど料金がかかります。API連携機能を使うことでアプリケーションの開発コストをおさえられたとしても、ランニングコストが膨れ上がってしまうこともあるため、導入時に料金体系について詳しく確認する必要があります。
知識がないと使いこなせない場合がある
API連携を行う際には、連携仕様を確認して、その仕様にあわせて連携部分を開発する必要があります。そのため、API連携に関する知識が必要です。
API連携の活用事例
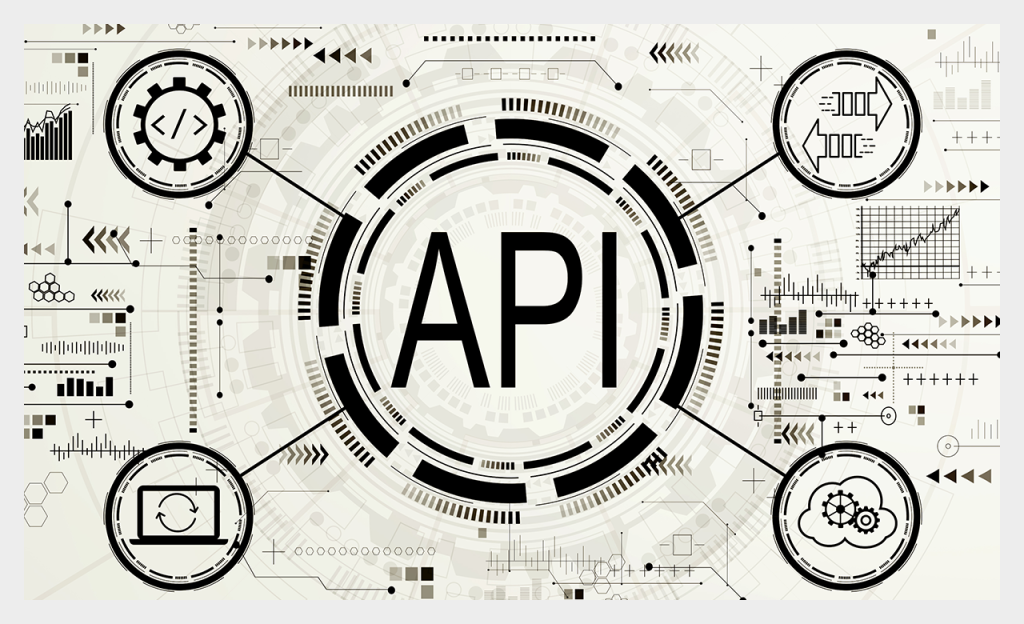
API連携の具体的な活用事例について紹介します。
SNS
ECサイトや会員サイトなどと、XやFacebookなどと連携させて、SNSのログイン認証機能を活用することが可能です。また、FacebookとInstagramを同時に投稿する、ワンクリックでWebサイトの記事をSNSで拡散するといった使い方もできます。
ECサイト
企業が独自に運営しているECサイトをほかのECサイトと連携させることで、商品情報を複数のECサイトに掲載することが可能です。自社の商品を大手ECサイトにも掲載することで、売り上げが伸びることもあります。
POSレジ
POSレジで収集された売り上げや在庫のデータを、ほかのアプリケーションと連携させることで、各店舗のデータを集計・分析でき、スピーディーに在庫管理やマーケティング戦略につなげられます。
クラウドサービス
GoogleやMicrosoftが運営するクラウドサービスと、自社で開発したアプリケーションやシステムを連携させることで、多くのサービスを活用できます。たとえば、ビッグデータの解析・ファイル共有・スケジュール管理など、クラウドサービスを連携させることが可能です。
社内システム
社内で業務に使われる会計ソフト、POSシステム・チャットツール・ワークフローシステムなどをAPI連携させることで、業務の効率化につながります。それぞれのシステムやツールを連携させれば、データの連携やワンクリックでの使用が可能です。
関連サービスについて
APIサービスの例
ここでは具体的なAPIサービスをご紹介します。
X API
SNSのXのAPIです。特定のキーワードやハッシュタグでポストを検索する、ユーザー情報を取得する、ダイレクトメッセージを一斉送信する、トレンドを分析するなどの高度な機能を利用できます。
Google Cloud APIs
Google Cloudのサービスと連携できるインターフェースです。ストレージ機能や機械学習ベースのデータ分析など、Google Cloudのさまざまなサービスとの連携が可能です。
LINE API
LINEのログイン機能やbotを作成して、応答メッセージを同時に送受信する機能を提供するAPIです。
OpenAI API
OpenAI APIとは、OpenAIが提供するGPTなどの機械学習モデルのAPIです。OpenAI APIを活用することで、文章生成や質問応答、自然言語理解などの機能もつモデルを、自社で開発するシステムに組み込むことが可能です。
OpenAI APIについてはこちらもご覧ください。
>>OpenAI APIとは?モデルの種類やできること、メリット・注意点を解説のページへ
API連携の実装手順
API連携を実装する手順は以下のとおりです。
①目的を明確にする
まずは、開発の手間をかけずにコストを削減したい、自社のシステムではできないことを実現したいなど、目的を明確にします。目的によって、連携するアプリケーションや連携の仕方が変わります。
②連携先の選定・登録
連携先を選定し、ユーザー登録を行います。
③APIキー・シークレットキーの取得
連携に必要なAPIキー、シークレットキーを取得します。
④実装・テスト
連携部分を実装し、テストを行います。
⑤運用と保守管理
アプリケーションの連携部分の運用がはじまります。連携仕様の変更などが生じた場合は、仕様を調査して影響確認を行う必要があります。
情シス特化型運用支援サービス紹介

お客様の情報システム部門を“守りの情シス”から“攻めの情シス”へ変革する「情シス特化型運用支援サービス」の紹介資料です。
DX全盛のいま、人手不足や仕組不足の課題から解放され、効率的な経営資源の活用を目指す“守り”から“攻め”への改革が情報システム部門に求められています。
SHIFTは、情報システム部門が行う業務の大半を占める定常・運用業務を可視化・効率化し、本来行うべき内製開発支援や中期経営計画など、経営活動や知的生産性の高い業務に集中していただくための支援を行います。
お客様の情報システム部門を“守りの情シス”から“攻めの情シス”へ変革する「情シス特化型運用支援サービス」の紹介資料です。
DX全盛のいま、人手不足や仕組不足の課題から解放され、効率的な経営資源の活用を目指す“守り”から“攻め”への改革が情報システム部門に求められています。
SHIFTは、情報システム部門が行う業務の大半を占める定常・運用業務を可視化・効率化し、本来行うべき内製開発支援や中期経営計画など、経営活動や知的生産性の高い業務に集中していただくための支援を行います。
まとめ
API連携とは、アプリケーションの機能を別のアプリケーションから呼び出す際に役立つ仕組みです。API連携の仕組みを活用すれば、新たにアプリケーションやソフトウェアを開発しなくても、すでにあるものを利用できます。
API連携を活用してアプリケーションやシステムの連携を進めたい場合は、SHIFTのDXサービス開発をご活用ください。それぞれのニーズやシステム環境にあった対応を行い、お客様のDX推進を強力にサポートいたします。
DXサービス開発なら、SHIFTにご相談を!
「社内に多くの業務システムがあるけれど連携が進まず、かえって効率が悪いのを何とかしたい」「外部システムなども活用してDXを推進したいが、人材不足やノウハウ不足でむずかしい」などの悩みをもつ企業様も多いでしょう。
この記事でもご紹介したとおり、API連携の仕組みを活用すれば、外部ツールや既存の仕組みを連携させて業務の効率化やコストの削減が可能です。しかし、API連携の仕組みを理解して開発ができる人材やノウハウがないと、開発を進めるのはむずかしいでしょう。また、外部ツールとの連携や既存ツールのデータ連携などを実現しなければ、社内のDX化も進みません。
そこで、SHIFTのDXサービス開発をご活用いただければ、そのような課題を解決できます。SHIFTの特徴は、独自に定義した価値基準「DAAE」や、開発手法により「売れるサービスづくり」を実現するノウハウです。DXやAIに関する豊富な知見や多種多様な業界ノウハウを活かして、お客様の業務やお悩みに対する最適なご提案をいたします。
API連携に関するよくある質問
Q1.API連携とは何ですか?
A.API連携とは、APIを活用して異なるアプリケーションやソフトウェア、プログラム同士を連携させることを指します。
Q2.API連携のメリットは何ですか?
A.業務に利用しているアプリケーション同士や外部のシステムなどと連携させることで、業務の効率化につながります。
たとえば、アプリケーションごとにデータを別々に用意する必要がなくデータを共有できる、それぞれのツールを別々に操作する必要がなくなり操作性が向上するなどのメリットを得られます。また、API連携を活用することで、それぞれのアプリケーションやシステムのなかに蓄積されているデータの連携が容易になり、データの加工や活用、共有などがしやすくなります。このほか、セキュリティが強化されることなどもあげられます。
Q3.API連携を導入する際に注意すべきデメリットは何ですか?
A.API連携機能は、開発したアプリケーションやシステムを幅広く活用してもらうために、開発側が用意する機能です。たとえば、XのAPI連携機能は、Xの開発側が用意しています。しかし、開発会社の方針が変わると、連携部分の仕様の変更やAPI連携の終了、場合によってはサービス自体が終了してしまうこともあります。API連携を利用する場合には、API連携の仕様変更や提供終了のリスクを検討しておかなくてはいけません。また、連携するアプリケーション側で何らかのトラブルが発生すると、連携機能を利用する側には問題がなくても、連携がうまくいかなくなる場合があります。このほか、リクエスト回数に制限がかけられている場合があることや、かえってコストが膨れ上がる可能性もあること、知識がないと使いこなせない場合があることなどもあげられます。

監修
永井 敏隆
大手IT会社にて、17年間ソフトウェア製品の開発に従事し、ソフトウェアエンジニアリングを深耕。SE支援部門に移り、システム開発の標準化を担当し、IPAのITスペシャリスト委員として活動。また100を超えるお客様の現場の支援を通して、品質向上活動の様々な側面を経験。その後、人材育成に従事し、4年に渡り開発者を技術とマインドの両面から指導。2019年、ヒンシツ大学の講師としてSHIFTに参画。
担当講座
・コンポーネントテスト講座
・テスト自動化実践講座
・DevOpsテスト入門講座
・テスト戦略講座
・設計品質ワークショップ
など多数
――――――――――
ヒンシツ大学とは、ソフトウェアの品質保証サービスを主力事業とする株式会社SHIFTが展開する教育専門機関です。
SHIFTが事業運営において培ったノウハウを言語化・体系化し、講座として提供しており、品質に対する意識の向上、さらには実践的な方法論の習得など、講座を通して、お客様の品質課題の解決を支援しています。
https://service.shiftinc.jp/softwaretest/hinshitsu-univ/
https://www.hinshitsu-univ.jp/
――――――――――



