Introduction
企業がシステムやアプリケーションを開発する際は、開発要件だけでなく、動作するマシン環境についても知識を得ておく必要があります。環境構築の仕方や性質などを知っておくことで、効率よく高性能な環境を選べるためです。
仮想マシンとは、仮想化技術を活用して、コンピュータ内に仮想的に生み出された環境のことです。いまや当たり前に活用されている仮想マシンの技術ですが、実は仕組みがよくわかっていないという方も多いでしょう。
この記事では、仮想マシンについて、導入するメリット、デメリット、種類などを解説します。


目次
仮想マシンとは
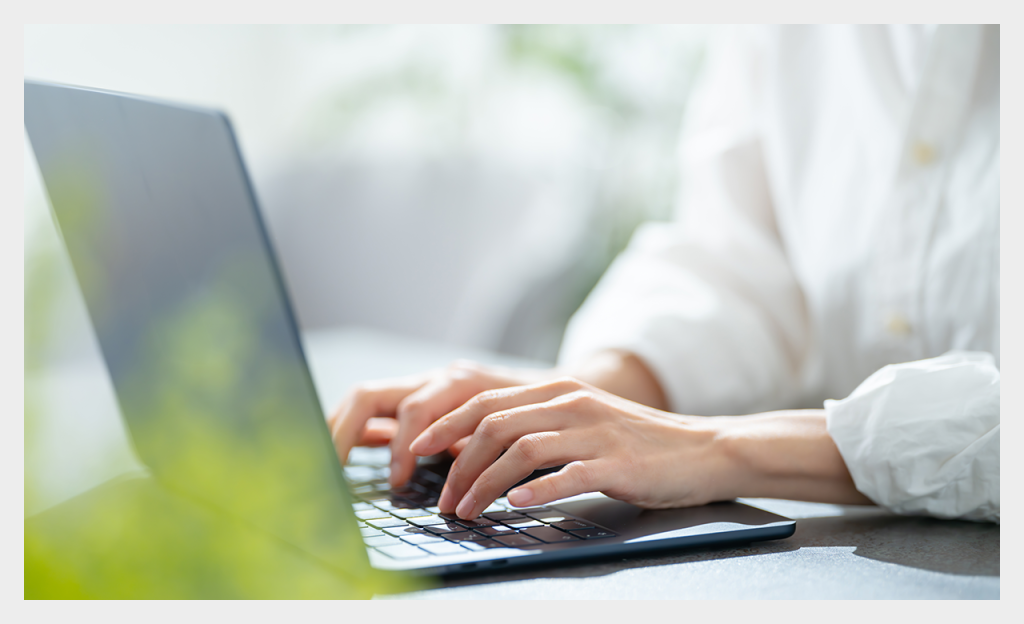
ここでは、仮想マシンとは何か、ホストOSとゲストOSの違いについて解説します。
物理的なハードウェア上に論理的に構成された仮想的なコンピュータ
仮想マシンとは、物理的なコンピュータ上に仮想的・論理的に構成されたコンピュータのことです。物理的にコンピュータを用意しなくても、ソフトウェア上でコンピュータの動作を実現します。仮想的につくり出された空間で動くため、仮想マシンと呼ばれているのが特徴です。
仮想マシンを構築するためには、最低でも一つ物理的なコンピュータが必要ですが、そのうえに複数の仮想マシンを構築することが可能です。一台のコンピュータしかなくても、複数の仮想マシンを構築でき、複数のコンピュータがあるかのように利用できます。
仮想マシンを活用することで、1台のハードウェアをより効率的に使うことが可能です。
ホストOSとゲストOSの違い
仮想マシンには、ホストOSとゲストOSという大事な概念があり、理解しておく必要があります。
ホストOSとは、仮想マシンでベースとなるコンピュータに搭載されているOSのことで、ゲストOSのために機能や場所を提供します。一方、ゲストOSは、ホストOSに招かれる側です。
ゲストOSは、ホストOSと異なるOSやバージョンでも動作できます。たとえば、Macのコンピュータに仮想マシン環境を構築し、Windowsをインストールしたとしましょう。このとき、Mac側がホストOSになり、ゲストOSはWindows OSになります。
ホストOSとゲストOSの構成の仕方の違いによって、仮想マシンにはいくつかの種類があります。そのため、ホストOSとゲストOSの仕組みについて、理解しておくことが重要です。
仮想マシンの種類と特徴
仮想マシンには、ホストOSとゲストOSの関係の違いによって、いくつかの種類があります。ここでは、その主な種類とその特徴について解説します。
ホストOS型
ホストOS型とは、ホストOSに仮想化ソフトウェアをインストールして、ゲストOSを構築するタイプです。ホストOS型の仮想化ソフトウェアとしては「Oracle VM VirtualBox」「VMware Workstation Player」などが存在します。
このタイプのメリットは、操作しやすく手軽に使えること、複数のOSに対応できることです。一方、ホストOSを介して処理が行われるため、処理速度の高速化がむずかしい、ホストOSにトラブルが発生すると影響が大きいなどのデメリットも存在します。
ハイパーバイザー型
ハイパーバイザー型とは、ハイパーバイザーと呼ばれる、仮想マシン機能に特化した専用ソフトウェアをインストールして実現するタイプです。仮想化に特化しているため、複数の仮想マシンを動作しても、高速な処理を実現可能です。ただし、コンピュータにハイパーバイザーと互換性がない場合は、新たにコンピュータを用意する必要があります。
ハイパーバイザー型の仮想化ソフトウェアには「Microsoft Hyper-V」「KVM」「VMware ESXi」などが存在します。
コンテナ型
コンテナ型とは、コンテナ管理ソフトウェアをインストールして利用する方式です。ほかのタイプとは異なり、ホストOS上にコンテナという独立した空間を複数作成して仮想マシンのように利用できる仕組みで稼働します。具体的なソフトウェアとしては、Dockerが有名です。
コンテナのテンプレートファイルであるコンテナイメージがあれば、仮想化環境を簡単にコピーできるため、環境構築が容易であり、ソフトウェアが軽量なこともメリットです。ただし操作が若干むずかしく、活用するにはある程度仕組みや技術を学ぶ必要があります。
Dockerについてはこちらもご覧ください。
>>Dockerとは?コンテナ型の仕組みやメリット・デメリット、利用手順を解説のページへ
仮想マシンのメリット

仮想マシンの仕組みを導入することで得られるメリットについて、解説します。
コスト削減とリソースの最適化が図れる
仮想マシンを活用すれば、複数のコンピュータを購入する必要がなく、開発環境や業務環境のコスト削減につながります。複数のコンピュータを購入して管理する必要がなく、1台のコンピュータで複数の環境を用意できるため、初期費用や運用コストの削減が可能です。
また、コンピュータの台数を減らすことで、初期費用の削減だけでなく、運用管理者の人件費の削減にもつながるでしょう。
障害発生時のリカバリ対策になる
仮想マシンを活用することで、障害発生時に最小限の時間で復旧できるようになります。
たとえば仮想マシンの仕組みを活用すれば、データのバックアップがしやすくなり、障害対策につながります。バックアップが万全なら、たとえば本社のデータセンターで障害が発生しても、支社のデータセンターを利用することが可能です。
セキュリティの強化につながる
仮想化の仕組みを使わずに、1台のコンピュータ上で複数のサービスを動作させることも可能ですが、この状態でサイバー攻撃を受けると、すべてが乗っとられる危険性が高いです。しかし、仮想化することで環境を分離できるため、そのリスクを軽減できます。
ただし、仮想化すればセキュリティ対策が万全、というわけではありません。仮想化後も、適切にセキュリティ対策を行う必要があることに注意が必要です。
複数OSでの動作検証が可能になる
一台のコンピュータ上で複数のOSを稼働できるため、複数のOSによる動作検証が可能です。たとえば、業務システムを開発して複数のOS上で問題なく動作することを検証したい場合などに、複数のコンピュータを用意する必要がありません。また、複数のOSの組み合わせによる検証なども容易です。
仮想マシンのデメリット
仮想マシンの仕組みを導入することによるデメリットについて、解説します。
物理マシンと比べパフォーマンスが低下する
仮想マシンの性能は、その性質上物理マシンの性能がベースになります。そのため物理マシン以上のパフォーマンスを発揮することはできません。高い性能を求める場合には、あえて仮想マシンを導入しないという選択肢もあるでしょう。
運用に専門知識が必要になる
仮想化技術についての専門知識や技術がないと、仮想化環境を構築・運用することはむずかしいでしょう。環境を構築して安定的な運用を行うためには、高度な専門知識や技術をもつ優秀なIT人材が必要になります。IT人材の採用や教育にコストがかかる場合もあるため、注意が必要です。
管理対象が増えセキュリティ管理の工数とライセンスコストが増える
仮想化環境を構築することで、コストや管理稼働削減のメリットを得られるのは、ある程度の規模をもつ環境を管理するときだけです。小規模な環境だと、かえって仮想化環境を管理する手間が増えてしまうでしょう。
そのため、仮想化環境を導入することで、コストや管理稼働の削減が見込めるか、現状の環境を正しく把握して見極める必要があります。
仮想マシンの活用事例
仮想マシンは、どのような場面で活用されているのかをご紹介します。
ソフトウェア開発のテスト
ソフトウェア開発の現場では、さまざまな種類のOSでの組み合わせ検証テストが必要です。上記でもご説明したとおり、複数のコンピュータにOSを用意してテストを行うと、コストがかかります。しかし、仮想化の仕組みを活用すれば、一つのコンピュータ上で複数のOSの検証が可能です。
ソフトウェアテストについてはこちらもご覧ください。
>>ソフトウェアテストとは?種類や目的、重要な7原則を紹介のページへ
さまざまな分野のクラウドで運用されているシステム
分野を問わずクラウドで運用されているシステムに、仮想化の仕組みが使われています。
たとえば自治体システムでは、オンプレミスと呼ばれる各自治体にシステムを導入するのではなく、仮想マシンによる運用が進んでいます。その結果、柔軟なリソース拡張や市民の個人情報のセキュリティ対策などに役立っているのです。
また、病院システムなども仮想化することでデータのバックアップが容易になり、障害や災害など万が一の事態に備えることが可能です。病院のカルテや診断結果などのデータが失われると診察に影響が出てしまい、最悪の場合は人命にも関わります。そこで仮想化マシンを活用することで、高い可用性を実現できます。
▽あわせて読みたい▽
>>基幹システムとは?ERPとの違いやメリット・注意点、選び方を解説のページへ
まとめ
仮想マシンとは、物理的なコンピュータ上に仮想的・論理的に構成されたコンピュータのことです。物理的にコンピュータを用意しなくても、ソフトウェア上でコンピュータの動作を実現します。仮想的につくり出された空間で動くため、仮想マシンと呼ばれます。
仮想マシンの仕組みは古くから活用されており、非常に重要な仕組みです。仮想化により、システムの開発や運用環境のコスト削減などにつながります。企業の業務システムや基幹システムを効率よく適切に運用するために欠かせません。
社内システムや業務システムのインフラ環境を改善して、効率化やコスト削減を図りたい場合は、SHIFTのインフラ設計・構築サービスをご活用ください。お客様のニーズや状況にあったインフラ設計・構築を行い、お客様のDX推進を強力にサポートいたします。
SHIFTではインフラ設計・構築・運用をトータルで支援!
「社内システムの運用コストがかかりすぎているため、改善したい」「業務の無駄が多いため、DX化を進めたい」「社内システムを改善したいものの、ITに詳しい人材がおらず、ノウハウもない」とお悩みの企業様は多いかもしれません。
この記事でもご紹介したとおり、環境の仮想化の仕組みを活用すれば、社内システムや業務システムの構築・運用コストの削減、性能の向上などが見込めます。しかし、社内のインフラ環境の再構築を行うと、業務に大きな影響をおよぼすため、慎重に行う必要があるでしょう。また、環境の再構築、改善などを適切に行うためには、インフラ設計・構築に関する専門的な知識や技術が必要です。
そこで、SHIFTのインフラ設計・構築サービスをご活用いただければ、お客様のビジネス要件にあわせたインフラ設計や構築を、企画から運用までトータルサポートいたします。DXに関する豊富な知見や多種多様な業界ノウハウを活かして、お客様の業務やお悩みに対する最適なご提案をいたします。
仮想マシンに関するよくある質問
Q1.仮想マシンとは何ですか?
A.仮想マシンとは、物理的なコンピュータ上に仮想的・論理的に構成されたコンピュータのことです。物理的にコンピュータを用意しなくても、ソフトウェア上でコンピュータの動作を実現します。仮想的につくり出された空間で動くため、仮想マシンと呼ばれているのが特徴です。
Q2.仮想マシンの主な種類と特徴にはどんなものがありますか?
A.ホストOS型、ハイパーバイザー型、コンテナ型の3種類があり、それぞれ操作性や導入の難易度、パフォーマンスなどに違いがあります。
Q3.仮想マシンのデメリットは何ですか?
A.仮想マシンの性能は、その性質上物理マシンの性能がベースになります。そのため物理マシン以上のパフォーマンスを発揮することはできません。高い性能を求める場合には、あえて仮想マシンを導入しないという選択肢もあるでしょう。また、仮想化技術についての専門知識や技術がないと、仮想化環境を構築・運用することはむずかしいでしょう。このほかに、管理対象が増えセキュリティ管理の工数とライセンスコストが増えることがあるなどもあげられます。

監修
永井 敏隆
大手IT会社にて、17年間ソフトウェア製品の開発に従事し、ソフトウェアエンジニアリングを深耕。SE支援部門に移り、システム開発の標準化を担当し、IPAのITスペシャリスト委員として活動。また100を超えるお客様の現場の支援を通して、品質向上活動の様々な側面を経験。その後、人材育成に従事し、4年に渡り開発者を技術とマインドの両面から指導。2019年、ヒンシツ大学の講師としてSHIFTに参画。
担当講座
・コンポーネントテスト講座
・テスト自動化実践講座
・DevOpsテスト入門講座
・テスト戦略講座
・設計品質ワークショップ
など多数
――――――――――
ヒンシツ大学とは、ソフトウェアの品質保証サービスを主力事業とする株式会社SHIFTが展開する教育専門機関です。
SHIFTが事業運営において培ったノウハウを言語化・体系化し、講座として提供しており、品質に対する意識の向上、さらには実践的な方法論の習得など、講座を通して、お客様の品質課題の解決を支援しています。
https://service.shiftinc.jp/softwaretest/hinshitsu-univ/
https://www.hinshitsu-univ.jp/
――――――――――

